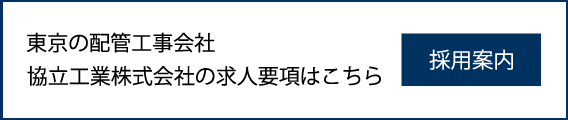お役立ちコラム
火災報知器にも種類がある?お悩み解決!選び方のポイント教えます
火災報知器の設置は消防法によって設置が義務付けられています。
公共設備だけでなく個人の住宅も同じです。
具体的に設置場所も法律によって定められていますが、知らずに未設置のまま放置している住宅がある状態です。
2011年以降設置が義務付けられていますが、知らない方も多いのではないでしょうか。
皆さんは火災報知器の特徴をどれほど知っているでしょうか。
正しい知識を持ち、自分の身を守るため安全対策を心掛けましょう。

Table of Contents
火災報知器ってそもそも何?
学校や公共設備など利用していて赤い丸に黒いボタンのついた発信機を見たご経験はないでしょうか。
先生に押してはいけないと注意された経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
壁についている赤い物体が火災報知器です。
個人の住宅には違った種類の白い火災報知器が設置されていますが役割は同じです。
主に火災を感知した場合や発見した方が周囲に知らせる装置として機能します。
一概に火災報知器といっても種類がさまざまで、住宅の状況や想定される火災現場によって種類が変わります。
天井に設置されている場合が多く目立たない存在ですが、住宅を守る縁の下の力持ちです。
一度自宅に設置されているか確認しておいてもいいかもしれません。
もし火災報知器がない場合は、この記事を参考に今すぐに設置してください。
火災報知器の種類は2つある?
火災報知器には大きく分けて2つの種類が存在します。
住宅をこれから購入する方は不動産と火災報知器の話をする機会が多くなるでしょう。
それぞれの名前や特徴を知っておくことでトラブルを防げます。
ほかの方に説明できるほどくわしくなっておきましょう。
住宅用火災報知器とは
一般的に家庭に設置される火災報知器は住宅用になります。
火災のときに煙や熱を感知し、警報を鳴らし周囲に知らせる役割を果たします。
就寝時や外出時の火災に対して、安全管理として設置されていますが、寿命や故障で作動しない場合もあるでしょう。
交換の目安は10年と言われていますが、電池切れを起こしている場合もあるため、こまめに確認すると安全に繋がります。
火災報知器が設置されていれば逃げ遅れる心配もなく、早急に対処が可能です。
注意点として単独でブザーを鳴らすタイプであり、ほかの施設に知らせるものではありません。
自動火災報知設備システム
自動火災報知システムとは住宅用と機能は変わりません。
火災があった際に感知し、知らせる機能を備えています。
ですが、大きな特徴としてほかと連携しているメリットがあります。
住宅用は単独でブザーを鳴らし周囲に知らせ、音を聞いた方が音が届かない周囲の方に連絡する必要がありました。
一方で、自動火災報知設備システムは感知器、発信機、受信機、非常放送設備などで校正されているため一定規模の建物に設置されています。
別名「自火報(じかほう)」と呼ばれています。
建物全体にブザーが鳴り響くため遠くにいる方にも火災を知らせる手段です。
どれがいい?火災報知器のポイントや選び方
火災報知器を選ぶ際に気をつけたいポイントがいくつかあります。
自宅の状況や環境、許容できる手間によって設置すべき火災報知器が異なります。
トラブルにならないようにしっかり考慮して選ぶようにしましょう。
報知器の反応タイプによって選ぶ
火災報知器は感知タイプによって種類が異なります。
火災が発生した際に生じる熱・煙・炎を感知して周囲に知らせる仕組みです。
段階的に煙、熱、炎と火事は周囲に広がっていき、影響を与え、大きくなっていきます。
どの段階で感知を促すかによって購入するタイプが変わってきます。
ですが、どれを設置すればいいか悩む方も多いでしょう。
熱感知式はサウナや岩盤浴など高温な場所に設置され、屋内用と屋外用に分かれます。
比較的価格が安く、費用を抑えて購入が可能です。
煙感知式は火災の早期発見を可能にしますが、複雑な仕組みのため価格が高くなる傾向にあります。
熱になる前に火災を感知できるため素早い対応を可能にし、生存確率が高くなるでしょう。
炎感知式は赤外線や紫外線を感知する仕組みですが、障害物があると反応しないデメリットがあります。
障害物がない映画館などに使用されている火災報知器です。
さまざまな火災報知器が存在していますが、住宅の形状にあった火災報知器を選ぶようにしましょう。
火災報知器によって稼働方法が異なる
火災報知器は稼働方法にも種類が存在します。
主に「電池式」と「電源式」の2種類に分けられます。
電源式は配線がともなうため設置場所が限られるデメリットがある火災報知器です。
一方で、電池式はどこでも設置可能な万能型といえます。
また、電池が切れそうになると「電池切れです」と知らせてくれる機能も備わっている便利さです。
火災報知器が目立つとインテリアの妨げになって嫌だなと思う方は電池式を購入すれば目立ちません。
充電式の電池を使用すると追加費用もかからずお財布にも優しくなります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
よく耳にする火災報知器にもこれだけの種類があり特徴も異なるため、驚いた方もいらっしゃるかもしれません。
火災は対策していてもいつ起こるかわかりません。
安全対策をしっかりと行っていても、電池切れや住宅の環境にあっていない火災報知器ではうまく作動しない場合も考えられます。
ですが、火災は誤作動で対応できませんでしたでは済まされません。
正しい知識を蓄えて自分の身を守り、周囲の安全に貢献する努力をしましょう。